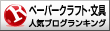今回はいわゆる「料理」ではありませんが、一般家庭の台所で全て賄えるモノ造りですので「男メシ」ジャンルに加えておきます
チャーハン編 麻婆豆腐編 たこ焼き編 手作り餃子編 カマボコ飾り切り編 まぐろ節ダシ編
若干コアですが勉強になる内容も含まれております、どうぞ最後までお読みください
はじめに
キニーネとは
カクテルなどのお酒で用いられることがある苦み調味料です
かつては世界中で流行していたマラリアに対する特効薬としての扱いでしたが、もっと良い薬が開発されましたので現在日本では医薬品としてほとんど使われていません
もともとはキナ(アカキナノキ Cinchona succirubra)という樹木の樹皮から抽出されていたものですが、グレープフルーツやレモンなどの柑橘系果皮にも含まれていることが分かり、一般家庭でも簡単に入手することができます
あとで詳しく
スポンサーリンク
キニーネの作り方
では作り方
キナ皮ではなくグレープフルーツ版です
グレープフルーツは無農薬でワックスなどが付いていないものが望ましいのです
ふるさと納税なんかだと無農薬の物が多いようですね
が
今回は思い付きで始めた作業なので、近くのスーパーに売られていたイスラエル産の防カビ剤で処理されたものを買ってきました
この場合表面の汚れや防カビ剤を落とすために重曹水に付けておきます
自宅の台所に重曹が残っているものと思い込んでいたのですが、残りがわずか6gしかありませんでした
大体、水100ccに対して重曹1g程度ですので600ccの重曹水にグレープフルーツを10~12分間浸しておきます

頭が1/3ほど出ちゃってるので10分後にひっくり返してもう10分浸け込み
その後、流水で全体を洗い流します
ではグレープフルーツを切っていきましょう
まずは上下5mm程度を切り落とします


その後側面の皮を順番に剥いていきます
始めは包丁で切り目を入れていきますが、途中からはミカンのようにバリバリ剥がせます
これを何度か繰り返します 必要なのは皮のみ
果実の部分はグレープフルーツが大好物の家内が綺麗さっぱり処分してくれました
鍋に入れひたひた(皮の一群の上端よりさらに2、3cm上)になるまで水を加えます

資料によっては、ガラス鍋やホーロー鍋が望ましいようですがウチにはそんなしゃれおつな器具はありませんのでステンレスでww
煮込み中の蒸気にも有効成分が含まれている、とのことで穴の開いていない蓋をして2時間ほど超弱火で沸騰させます

ザルや網ボウルなどで濾して完成
出涸らしの果皮はさすがに使い道がないのでポイ
こうして「いかにも」な液体が出来上がりました

肝心のお味のほうは、というと・・・
激苦い!!
もうまさに、レモンやグレープフルーツを構成する味のうち、苦みだけを抽出、凝縮した苦さ(まんまやん)
さらに漢方薬などに通じる「薬剤臭さ」系の風味が伴っています
また最初にガツンっ!とくる苦みのみならず、後味がスゴイのよコレが
数分~10分程度、ずーっと独特の苦みが口の中で残り続けます
完全に大人向けの苦み調味料と言っていいでしょう、苦み耐性のない子供さんにとってはトラウマレベルの衝撃ですww
逆に、カクテルなどお酒が好きで、刺激に飢えている方々にとっては朗報
炭酸系のカクテル全般に少量のキニーネを混ぜると上手い具合にパンチの効いた味に変貌いたします
ソーダ・サイダー・ラムネなどと比較して甘味の少ない炭酸飲料のような認識ですが
本来はキニーネなど柑橘系の苦み成分が含まれた炭酸飲料のことを指し、17世紀のイギリス東インド会社の人間が、赴任先のインドでマラリア予防にジントニックとして飲んでいたのが始まりと言われています
ちなみに
私はお酒に弱いのでノンアルコールのカクテル主体
ですが苦み耐性はかなり高い上に、漢方薬や病院の消毒薬などの匂いも嫌いではなく(むしろ好き)どうやらこのキニーネと非常に相性が良いことが分かりました
いろいろ混ぜて試してみようと思います
スポンサーリンク
マラリアとキニーネ
さて、あとはお勉強の時間です
まずはマラリア
マラリアは、熱帯から亜熱帯に広く分布するマラリア原虫による感染症である。雌のハマダラカが媒介するマラリア原虫が病原体である。
蚊に刺されてマラリア原虫が体内に入ると、潜伏期間(1週間~4週間程度)を経て、発熱や悪寒(寒気)、頭痛、関節や筋肉の痛み、関節痛、筋肉痛、嘔吐、下痢といった症状が現れ、脳や内臓に合併症を引き起こすこともある。防蚊対策のほか、予防薬や治療薬もあるが、熱帯熱マラリアでは発症から24時間以内に適切な治療を施さないと重症化して、死亡することもある。悪性の場合は脳マラリアによる意識障害や腎不全なども起きる。
マラリア - Wikipediaより一部改変
いまから3000年近く前のギリシャや中国の文献などにもマラリアと思われる病状が記録されており、現在においても世界中で人類の脅威となりうる病気です
マラリアに対する治療法として、初めてその効果が確認されたのは、キニーネを含むキナノキの樹皮によるものである。マラリアの歴史 - Wikipedia
で、そのキニーネ
序盤にも紹介しましたがもうちょっと詳しく
薬効・薬理は 抗マラリア作用、解熱作用、抗不整脈作用、子宮収縮作用
その他、苦味健胃薬、強壮薬
この歴史を調べてみるといろいろ面白いエピソードがありまして・・・
元々の原料はグレープフルーツではなく、南米アンデス山脈原産のアカキナノキのキナ皮
マラリアに対する薬効が判明してからはイギリスをはじめとする欧米列強が自国の植民地経営に資する目的で世界中に移植栽培を進めていきました(上のジントニックの話に繋がります)
初めて移植栽培に成功したのはオランダで、以降、キナ皮の生産量が多いのはかつてオランダ植民地であったインドネシアのジャワ島です
本邦でもキニーネの国内生産を目指してキナノキの移植栽培に力を入れた時代があります
オランダ留学経験およびジャワ島滞在歴のある榎本武揚が1874年、明治政府に対しキナ導入の建議をおこなったのを皮切りに
多くの先人達の努力により1922年に当時日本の一部であった台湾においてキナノキの大規模栽培が可能に、また1934年には国内産のキニーネを製造することに成功しています
 キナの国内栽培に関する史的研究,南雲清二,薬学雑誌,131,1527―1543(2011).
キナの国内栽培に関する史的研究,南雲清二,薬学雑誌,131,1527―1543(2011).
これを記念して、明治神宮への奉納、宮家への献納がおこなわれたところを見るに、国家事業に近い形で推進されていたことが伺えます
このころから抗マラリア薬として重宝されたのは言うまでもなく、あらゆる疾病に効く万能薬的な扱いも受けましたが
1971年以降、副作用の問題で風邪薬など家庭薬に配合することが禁止され、合成マラリア薬の登場によりキニーネの需要は激減しました。
(なお、グレープフルーツ抽出の濃度では副作用の心配はありませんが、気になる方は飲用をお控えください)
そして第二次世界大戦期
開戦劈頭に一気に版図を拡げた旧日本軍はシンガポールとインド洋東側エリアからイギリス軍を追い出しました
最盛期にはアンダマン・ニコバル諸島まで手中に納めたのです
これら島内ではすでにキナノキが繁殖しており部隊内でのマラリア蔓延を防ぐために軍医がキニーネを製薬していました
一部は島民の治療にも使われていたといわれています
軍隊内では、本国からの補給物資でいろいろ賄うわけですが、足りないものは現地調達をおこないます
現金で支払うこともありますが主に軍票がもちいられていました
(以下文献引用)
アンダマンに渡ってから一時は軍票が使えましたが、すぐに軍票は原住民からキャンセルをくうようになってしまいました。
「壁にはるほどたまったのでもういらない」というのです。
そうなると原始的な物々交換以外に方法はありません。となると、このマラリアの特効薬が軍票より優秀な貨幣になってしまったのです。
兵隊たちは飲んだふりをして、ためておいては物々交換の貨幣の代用にしていたのです。
吉村正「離島百話」保険銀行日報社, 1977年
(引用終わり)
軍隊内のマラリア感染症の抑制効果は落ちてしまいますが、結果的に島内にキニーネが行き渡ってしまうという現象が起きていたのです
つまり
植民地経営を円滑に行うためにキナノキを各地に移植したイギリス東インド会社
さらに軍隊を病気による戦力低下から防ぐための軍需品としてのキニーネを製薬した旧日本軍
いずれも自分達が必要であるがために作り上げたシステムであることは間違いないのですが
同盟組んだり、敵同士で殺しあったりした両侵略者(島民にとって)が、期せずして協力関係となり
多くの島民を病気から救った、という側面もあるわけです
いやー、歴史ってホント面白い
そして今夜もノンアルカクテルに苦みを加えて晩酌でござる