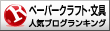少し文化的な話をしましょうか
久しぶりに、親バカ自慢したい芸術作品をゲットしましたので記事にします
皆さんは「千字文」ってご存じですか?
私は知りませんでした
まず現物を見てもらいましょうや これが千字文

いちおう各文字が判別できる程度の高解像度版をうpしました
(名前と落款印の部分は加工済み)
なーんかすごくね?
当家の長女ころも の作品です
次女KOHAKU と 三女なすなす は当ブログでも度々登場するのですが
長女ころも は比較的露出が少ない
これはですね
けっして芸術的、あるいはクリエイターとしての才能が無いわけでは無く
むしろ私を含め妹2人よりも作品が高尚であるがゆえに、なかなかブログでは紹介しにくい、という側面があります
( ´-`).。oO( お堅い作品が多い、とも言える)
スポンサーリンク
さて、今回のテーマ「千字文」
調べてみました
『千字文』(せんじもん)は、子供に漢字を教えたり、書の手本として使うために用いられた漢文の長詩である。すべて異なる1000の文字が使われている。千字文 - Wikipediaより
規模はかなり異なりますが、日本で言うところの「いろはうた」に近いものと推察されます
書家や書道家と呼ばれる方々にとっては、かなりメジャーな部類の詩文だそうです
作品として残すためには、1字のミスも許されないという
かなりの精神力と集中力を要する荒行ではありますな
( ´-`).。oO( 実はあとから修正も許容されているらしいが・・・)
私自身は
普段書きの字はかなり雑い
ただしお手本の模写だけは得意だったので習字の授業の成績は良かった
したがって
当然ながら書の道にはとんと疎く
「千字文」
と言われても
( ´_ゝ`)フーン・・・
ってなもんでしたが、いろいろ調べているうちに
ありました
私の食いつきポイント!!
食いついたのは、書そのものや個々の文字の出来栄え
ではなく
その成立過程と歴史についてです
スポンサーリンク
という点を掘り下げて、その他のwikiも読んでみますと・・・
『千字文』は、武帝が皇子たちに書を習わせるため、王羲之の真蹟から1,000字を選ばせ、それを一字として重複することなく、四字句ごとに計250句からなる韻文としてつくらせた、初学者を対象とする習字・書道の手本であり、漢字習得用の教材である[4]。文は、「天地玄黄、宇宙洪荒」(天地は玄黄なり、宇宙は洪荒なり)から始まって「謂語助者、焉哉乎也」(語助と謂うは、焉、哉、乎、也)で終わり、暗誦に便利なように押韻がなされている。また、限られた字数のなかで最大限の知識や漢民族の伝統文化を継承させるよう工夫されており、森羅万象を網羅しながら倫理教育の用も兼ねている。
となりますね
いや、なるんですって
なるという前提で話を進めます
ちなみに歴代で「武帝」を諡(おくりな)された皇帝は12人います
武力を中心に国を立ち上げた皇帝は、だいたい伝統的に「武帝」なのです
じゃあどの武帝?
↓↓↓この武帝
概要
南朝・梁(502年 – 549年)の武帝が、文章家として有名な文官の周興嗣(470年 – 521年)に文章を作らせたものである。周興嗣は、皇帝の命を受けて一夜で千字文を考え、皇帝に進上したときには白髪になっていたという伝説がある。(中略)完成当初から非常に珍重され、以後各地に広まっていき、南朝から唐代にかけて流行し、宋代以後全土に普及した。千字文 - Wikipediaより
梁(南朝)
分かりますか? 分っかんないですよね
( ´-`).。oO( いや、今回に限り私は知ってるよ めっちゃ)
上記「概要」の時代背景を少しでもイメージできるよう
ここで
歴代中華王朝・帝国の名称の覚え方を皆様に伝授しましょう
世界史選択だったらご存じかも知れませんが、何も見ずにそらで歌える方はそれほど多くないでしょう
「もしもしかめよ」のメロディーに合わせます いきますよ
殷周秦漢三国晋(〽いんしゅうしんかん さんごくしん)
南北朝隋唐五代(〽なんぼくちょうずい とうごだい)
中華人民共和国(〽ちゅーかじんみん きょうわこく)
このライト層向けの覚え方には梁(南朝)は出てきません
「南北朝」として一纏めにされているためです
一般的にはマイナーな王朝ということです
というわけで
もう一つ童謡に合わせた歴代王朝の覚え方があり、より詳しく羅列されています
世界史選択で大学受験する気であればこれぐらいは歌えないといけません
「アルプス一万尺」のメロディーでいきます 付いてきてくださいよ
殷周東周春秋戦国(〽いんしゅうとうしゅう しゅんじゅうせんごく)
宋斉梁陳隋(〽そうせいりょうちんずい)
隋唐五代十国宋金(〽ずいとうごだい じゅっこくそうきん)
中華民国や中華人民共和国は省略されています、それぐらい知ってて当たり前の上級者向けの覚え方です
歌詞の中で隋のみ同一王朝が被っていますが、ほかの同名王朝はそれぞれ別物です
これでもなお
春秋五覇の 晋・秦・斉・楚・宋(諸説あり)
戦国七雄の 韓・魏・趙・斉・燕・楚・秦
五代十国の
後梁・後唐・後晋・後漢・後周 + 前蜀・後蜀・呉・南唐・荊南・呉越・閩・楚・南漢・北漢(諸説あり)
などは網羅できていません
ひたすら中華の歴史は奥が深くてややこしい!!
だがそれがいい! それが面白い!!
さて、梁(南朝)がどこに出てきたか気づきました?
もう一回上級編の歌詞を見てね
1か所赤文字になっていたのが分かりますね
この時代です
でも
まだピンと来ないですよね
なんせ画数の多い漢字がひたすら並んでいるだけですから
スポンサーリンク
ではこうしましょう
 https://www.kotoken.co.jp/ceradata/chronological/chronological-table.htmlより一部改変
https://www.kotoken.co.jp/ceradata/chronological/chronological-table.htmlより一部改変
分かりますかね
梁(南朝)の前にたくさん王朝名が並んでいますので、かなり時代が進んだ後のように見えますが
その頃の日本はまだまだ古代
感覚的には昔々のその昔
大陸ではすでにこんな高度な書の文化が完成していたわけですよ
そして日本に伝わったのは
考古学では各地から見つかる律令期から奈良時代の木簡のなかに、文字の練習や書籍の文字を書き写したものがあり、それを習書と総称するが、この習書木簡に多く観られるのが『論語』と『千字文』であるため、漢字を学ぶ手本として比較的はやく大陸からもたらされたと考えられている。千字文 - Wikipediaより
ということらしいです
今も昔も舶来モノは珍重される風潮が我が国にはありますので、千字文の成立から間を置かず日本に伝わってきていたようですね
「なにこれすごい 巷で流行ってる?」→よし持ち帰ろう
あるいは持って行ってやろう
ぐらいのノリだったのではないか、と
スポンサーリンク
ちなみに梁(南朝)
かの有名な「平家物語」の冒頭部分にもチラっと出てきます
みなさん古文の授業で暗唱させられましたよね
沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす
驕れる人も久しからず ただ春の夢のごとし
猛き者もつひにはほろびぬ ひとへに風の前の塵に同じ
ここまではソラで言える人も多いでしょう
もそっと先です
遠く異朝をとぶらへば 秦の趙高 漢の王莽 梁の朱忌 唐の祿山
これらは皆舊主先皇の政にもしたがはず 樂しみをきはめ 諌めをも思ひ入れず 天下の亂れん事を悟らずして 民間の愁ふるところを知らざりしかば 久しからずして 亡じにし者どもなり
奸臣の代名詞として挙げられるほどの悪名が日本にも伝わっており
梁(南朝)そのものが比較的メジャーな王朝として認識されていたものと推察されます
( ´-`).。oO( wikiみるとヘマはしてるけど悪人じゃないのよね、朱忌さん)
余談でした
スポンサーリンク
このように
歴史好き+親バカ が高じてしまうと
千年以上前から数多の人を介して伝わった書のお手本を、令和の時代に「うちの子」が書いている
という情景に壮大な歴史のロマンを感じ、親バカがさらに極まっていくのでありました
(-_-).。oO( いや、いいんだ ただの自己満足だよ・・・)
さて、もう一度「千字文」を見てみましょう

まぁまぁ大き目のダイニングテーブルに収まりきらないほどの大作です
いやーもうね、圧巻のひとことですよ
書の素人たる私から見たら「あら、上手」「すげぇな」以外の感想は無いのですが、これでも書の世界では
「まだまだ」らしいです
これまた奥が深い世界ですこと
今回は書家としての ころも の作品でしたが
当家にはもう一人書家がいます
ころも の母親、私の家内ですがさらにハイレベルな書家活動をしているようです
家内=毎日系
ころも=読売系
だそうですが素人の私にはその価値がイマイチ表現できません
相当な腕前のはずなのですが、まだまだ師匠に習っている身、ということで作品を世に出すのを(っていうか私のしょぼブログごときに掲載するのを)嫌っておりまして
ちょっと勿体ないような気もします
本格的に「道」が付く世界は、歴史的にも、規模的にも桁違いの奥深さがありますので当事者以外には計り知れない部分がありますね
また機会があれば紹介してみたいと思います
かくして
「千字文」の歴史背景や中華王朝変遷の流れをころもと家内に熱く語ってはみたのですが
日本史選択だった2人にはイマイチ伝わらなかったようです
(´・ω・)「あ、はい」
(°ω°)「・・・お、おう」
同じ「千字文」について語っているハズなのに、全く会話が嚙み合わない我が家の一風景なのでありました・・・合掌