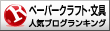引き続き、私の趣味バリバリの話題で参ります
軽~いノリで読み進めてください
前回は、軍用艦としては絶滅してしまった帆船について、でして
物語としては完結しました
本編では船のキール変遷を軸に、生き残った帆船がどのような進化を遂げていったか
というお話を続けていきましょう
これまでのおさらいです
と紹介してきました
当時ライバル同士であった、太陽の沈まぬ国大英帝国と新進気鋭のアメリカ合衆国
数年に1度開催される世界最古の近代スポーツ大会
 「100ギニーのロイヤル・ヨット・スクォードロン・カップ」改め「アメリカスカップ」- Wikipedia
「100ギニーのロイヤル・ヨット・スクォードロン・カップ」改め「アメリカスカップ」- Wikipedia
このカップを巡って熾烈なレースが繰り広げられていた19世紀後期
第1回(1870年)、第2回(1871年)、第3回(1876年)と
ここまでの大会は、元祖優勝艇である「アメリカ号」とよく似た形の2本マストスクーナーが主流であり、船型に大きな変化はありませんでした
その後クラスルールなどの整備により第4回(1881年)大会からは1本マストのヨットに変更されました

それぞれ代表的な船を提示しています
そして今回ピックアップするのは1本マストタイプ(初期)の代表格
第9回(1893年)大会で惜しくも敗れたヴァルキリー2(Valkyrie2)です
なぜこの艇を選んだか、というと
名前がカッコイイからです
以前の記事で紹介したBluenose(漁船)よりも、さらに船底部分が中央に圧縮されてきており、海中深く突き刺さるようにキールが伸びてきていますね

(´-‘).。oO(画質が荒いのはファイルを軽くするため、いずれYouTubeにまとめる予定)
(´-‘).。oO(キール形状の変遷を中心に追っているので建造年代が前後するのは気にしないように)
このように、今までは船底の構造材や錘でしかなかったキールは横流れ防止の安定板的な役割も持つようになってきます
ちなみに時代が進んで安定板としての役割だけを抽出するとこういうことになります↓
スポンサーリンク
一方、水上の形状はというと
当時のクラスルールは艇の水線長とセイル面積の2つのパラメーターのみで計算されるので
(´-‘).。oO(ちゃんとした計算式もあるのですが、解説できるほど理解が深くないので割愛)
前方ではバウスプリットを目いっぱい突き出し
後方ではブームを目いっぱい伸ばして

とにかくセイル面積を大きく稼ごうとする形状になってきます
当然セイル面積が大きい方がより多くの風を受けることができ、推進力が増すのは容易に想像がつくでしょう
それに対し船体は相対的に小さくなっていき、いつしか非常に不安定な船ばっかりが出来上がるようになりました
重大な事故が起こったという記録は見当たりませんでしたが、危惧はあったものと思われます
このような対策として新たなクラスルールが策定され、より洗練されたヨットが出来上がっていくわけですが・・・
(´-‘).。oO(ちゃんとした計算式もあるのですが、解説できるほど・・・以下略)
次回 アメリカスカップに深く、長く関わる、ある人物の紹介をしたいと思います
皆様の家庭の食卓に少なくとも1回は登場したことがあるであろう商品、あのイギリス発祥企業の創始者です
意外と知られていないヨット狂で、とても熱い物語の主人公となります
次の記事はコチラ
スポンサーリンク
表題の「草創期」
物事の始まりの時期を表す言葉で
雑草が無秩序にひたすら伸びていく様が、今回のセイル巨大化競争にピッタリ当てはまるような気がして使ってみました
この後もイギリスとアメリカの因縁は深まるばかり
第二次大戦後には2国以外の国も参加するようになり、アメリカスカップは混沌を極めるようになります
これはもうちょっと先の話